|
|
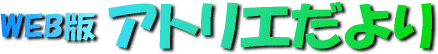
『アトリエだより』はアトリエでのこどもたちの様子を
ご家庭にお知らせするため毎月1回発行している教室通信です。
(Web公開用に記事を再編集してあります)
|
|
2006年04月
【4月前半の課題】
新学期が始まりました。皆さんひとつずつ進級おめでとうございます。絵の課題は石津ちひろさんの詩「あした」をテーマにしました。
新しいクラスになって、やりたいこと、目標にしたいことなど「新しい私」を思い描き、絵にします。詩を朗読すると楽しいということも感じてもらいます。7文字しか使ってないのに深みのある言葉の世界です。文字の読めない子は読める子が読むのを耳から聞いて世界を感じます。子どものための詩集もたくさん出版されています。おうちでも是非声に出して、詩の世界を楽しんでください。工作は「ゆらゆら人形」です。基本的なパーツ、頭、胴体、手、足に分けて描き、糸でつなぎます。体の部位を意識して作るのが狙いです。特に肩はかなり上で糸をつけないとバランスが崩れます。活動の中で、小さな失敗を経験することもしてほしいと思っています。自分でバランスがいいのか悪いのかの判断をできるためには経験が必要です。人形は動きがおもしろいので、それだけでも楽しめますが、いくつも作って、ごっこ遊びや劇もできます。
 5日(水1,3) 5日(水1,3)
来た人から詩を朗読しました。簡単そうで読みにくい詩に「あれ!」と戸惑いながら楽しみました。絵画の課題には、縄跳びや大好きな理科の授業の様子、サッカーや、キャンプをテーマに描く子がいました。ゆらゆら人形も楽しんで作っていました。自由工作をする子も多く、空き箱で「金魚の家」(紙なのでぬらすとぶよぶよになるよと声をかけましたが「いいの」と水を入れていました。)ロング貯金箱、電車、飛行船のタワー、前回課題(簡易アニメーション)の別バージョン、前回からの続きのジャンピングロケットなど様々なものが作り出されました。
 8日(土) 8日(土)
詩はそれぞれに朗読し楽しみました。一年生になって学校の絵を描く子、ゆらゆら人形が気にいって二つ作った子もいました。自由工作で、材料を持ちこみ、弓矢、消える貯金箱を作る子、布で野菜やウサギの人形を作る子もいました。
 12日(水2,4) 12日(水2,4)
詩は早口言葉のように「早く読みたい」という子が多く最後は笑い転げていました。小さな子とは一緒に一音ずつ読みました。小さな子は詩にとらわれず、好きなように絵を描きました。カブトムシ、ハムスター、鳥などの世界を描く子、自由に描きはじめ、「汚くなったー」というので、そこから対話をして、最終的には「洞窟の中の金」を金色の絵の具で描いた子などいました。新一年生は3人とも好きなキャラクターを描いていました。ゆらゆら人形は、がい骨やクリオネなど変わったモチーフが見られました。自由工作では、おはじきゲーム、ビー玉ゲームを作った子もいました。新4年生の男の子たちはおしゃべりに花が咲き、なかなか進みませんでした。新しい学期が始まり、不安なこともあるかもしれません。気の会う仲間と寄り添って話をすることで、ストレス解消をしていたのかなと考えます。でも最後にはそれぞれ作品を仕上げました。体験の方一名いました。
それぞれのご家庭でも、一緒に遊ぶ、対話をする、ということを通じて、お子様の心に寄り添ってみてください。課題をしないとやめさせるという脅しはしなくても結構です。貴重な一時間半ですので、課題をしない場合は、自分ですることを大体でも決めてくると、有効に時間が使えることを理解させるようにして下さい。また特殊な材料は持参してください。絵を描くこと、ものを作ることはその過程で、気づいたり、考えたりすることに大きな意味があります。結果を気にするよりも、まず、一筆描き出す、作り出すことから、始まります。自分自身の意志で行動し、自分の頭で考え、自分の手で作り出すという、本来の創造する喜びを、実感させてあげたいと思っています。取り組み方はお子様一人一人違いますので、それぞれにベストの方法で対応したいと考えています。
 14日(金) 14日(金)
年齢の低い子の多いクラスなので、少し難しい詩ですが、逆にあまり詩の内容にとらわれず自由に描ける題材でもあります。なんとなく雰囲気が伝わればいいのです。詩は理解するものでなく、味わうものだからです。遊園地や、学校、縄跳びの絵が描かれました。ゆらゆら人形を作った子も何人かいました。大人から見ればただつなぐだけの作業も、子どもにとってはテープひとつの長さを決めることから、難しいことです。こういう経験をしながら、予測をたてて動くということを覚えていきます。自由工作では、宝物箱、太鼓を作った子がいました。
季節柄、保護者の見学が多いので、気をつけていただきたいことを書いておきます。課題はできないといけないものではありません。年齢も個性も違うのですから、課題はきっかけと考えてください。ほかの子と比べて、できていないと感じられても口も手も極力出さないでいただきたいと思います。比べることはナンセンスです。子ども一人一人の感覚や違いを認め、価値の優劣でなくそれぞれの想いを表現できるようにしていきたいと思います。「できないよ」ということを私に伝えることも大事なことです。自分の気持ちを相手に伝えるということを自然なこととして身につけてほしいと思っています。親には甘えてしまいがちです。親も養護しがちになります。でも、これから先の人生では、親のいないところでひとりで立って歩いていくのです。生きる力を育むためにもコミュニケーション能力は育てていかなくてはなりません。できないことはこれからできるようになればいいのです。先回りして大人が手を出してしまうと、何ができて、何ができないのか、出来ない時に何に戸惑っているのか、本人もわからなくなってしまいます。私も一人一人が、どのような子か、長年来ている子でも今日はどんな調子かを観察しながら、次にどういう言葉がけをすればベストなのかを考えながら進めています。どこをどう引き出すのかはその時の様子で変わります。技術的なことは後からついてきますので、こういう絵が描きたい、こういうものを作りたいと、創造の喜びを感じて作品が生み出せるようにもっていきたいと考えています。
マルチメディアなどの情報化が進展する中、21世紀を生きるこどもたちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、学び、考え、主体的に判断し行動し、よりよく問題を解決する能力です。こどもの美術教育は基本の指導をしながらも、多様な造形体験を通して、創造の喜び、自己調節と協力(自らを律しつつ、他人とともに協調し、他人を思いやる心)そして上記の能力を育てることを大事にしています。
そのため、基本的に、子どもたちだけの活動場所として、アトリエがあると理解してください。見学する場合も、子どものありのままの姿を受け入れ、見守る形にとどめておいてほしいと思います。(トイレは和式で一階にありますので、一人で難しい子は補助をお願いします)
【4月後半の課題】
絵の課題は春の花「たんぽぽ」です。花びらがたくさんあって難しそうですが、中心から放射状にきれいな円形になるように、丁寧に描くことでタンポポらしさが出ます。葉の形状もユニークです。工作は粘土を使った小さな花瓶です。ビーズを埋め込んだり、乾いてから絵の具を塗ったり、粘土に絵の具を混ぜ込んだり、様々な方法で作れます。粘土は手でよく揉むとう作業が大事です。技術上必要なことでもありますが自分の手で練ることで感触を確かめ、いろんな形に変化する不思議さを感じてもらいたいのです。花瓶が見本ですが、別のものを作りたいと思うのはごく自然なことで、広がるアイデアで作っていけることも素敵なことです。粘土を揉みながら、頭の中で、イメージを膨らませるという時間はとても重要で、ある意味、一番大事にしたいポイントです。
 19日(水1,3) 19日(水1,3)
粘土はみんな大好きで、絵の具を混ぜ込んで作るのが人気がありました。ビーズをつけるのも意味のあるモチーフを描く子、抽象的な模様にする子、がいます。粘土そのものを楽しめる子が多いように思いました。前回の続きの絵を仕上げた子もいました。K君は、タンポポの横においてあったわたぼうしを見つけて「わーきれい。タンポポよりこっちを描く。小さい紙でいいよ」と感動の気持ちを持って描きました。自由工作では飛び出す玉や、割り箸と輪ゴムを使った変身する4連棒を作り、作品解説や、遊び方を説明してくれました。
 22日(土) 22日(土)
粘土はこのクラスも全員がしました。ひとつでは物足りなくて、いくつも作る子もいました。後半はタンポポの絵を描いた子もいます。花のつき方をよく観察して、中心から放射状に花が広がる様子を描ける様にお話して進めました。他2名体験の方いました。
 26日(水2,4) 26日(水2,4)
粘土を見ると、みんな創作意欲満々で、始めました。花瓶だけでなく、お金や、たらこ、おにぎりなどおもしろいモチーフがたくさん出てきました。型抜きして、クリップを差込みペンダントトップも作った子もいます。花瓶の模様にピカチュウが出てきてまだまだ根強い人気があると感じました。ムードメーカーのN君が物まねでみんなを楽しませてくれました。口も滑らかですが手も今日はよく動き、タンポポの絵も描きました。Rくんも、制作後、バスごっこ(寝転んで、柱の間を行ったり戻ったりする遊び)を楽しんでいました。仰向けになってお友達を乗せてあげるのですが小さい子達は喜んで、何度も乗せてもらっていました。
 28日(金) 28日(金)
粘土に絵の具を入れる作業はみんな大好きです。思い思いの色で作りました。K君と今日見学に来たA君が同じクラスでお互いにびっくりしていました。自由工作では、水時計を作った子がいます。タンポポを描いたEちゃんはあまりこちらから口を挟まず、自由に描かせたほうが、いい絵ができるようです。Yちゃんは黒い紙によく観察して綿毛を丁寧にクレヨンで描きました。コラージュ技法で仕上げをしました。Tくんはタンポポの特徴をよく捉えています。自由に粘土を使ってもらうと、刻んだり、こねたり、粘土という素材を丸ごと楽しんでいました。素材と遊び、楽しむことは五感を発達させます。
こどもの美術教育では知識や手先の技術よりも、作る楽しさや夢をまず感じ取ってもらいたいと思い進めています。自由にしていいよと言った時に生き生きと好きなものを作る、お子さんの心に寄り添ってあげてください。親の色に子どもを染めるのではなく、子ども自身が描くもの、作るものを丸ごと受け入れる、すなわち、君は君のままでいいんだよと、丸ごと受け入れて抱きしめてあげて下さい。
|
|
| [ こども図画工作教室 ] |
 |
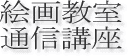
■会費制の通信講座です。 |
< デッサン・油絵・水彩画 >
全国どこからでも参加できます。
[ Click
] |
|
|