|
|
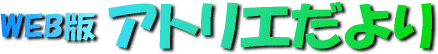
『アトリエだより』はアトリエでのこどもたちの様子を
ご家庭にお知らせするため毎月1回発行している教室通信です。
(Web公開用に記事を再編集してあります)
|
|
2006年12月
【12月前半の課題】
クリスマス、お正月と、子どもたちにとっては楽しいことがいっぱいの12月です。クリスマスカードや年賀状がつくれるように絵の課題としてはんこを作ります。スポンジを使用するので、はさみで簡単に作れます。工作は福引器です。ティッシュの箱と、割り箸で手軽に作れます。クリスマス会などイベントに使えて楽しい工作です。おうちでも楽しんで下さい。
 6日(水1,3) 6日(水1,3)
Y1ちゃん、Y2ちゃん、Hちゃんはいのしし模様や、オリジナルデザインのはんこ、K1くん、Nちゃん、Aちゃんはクリスマスツリーの模様のはんこを作りました。ツリーは形が難しくて描けないというので、三角模様を3つ組み合わせました。鋭角をきれいに切る方法を練習しました。K2くんは福引器を見ると張り切って作りました。Tくんは前回の続きのトナカイを仕上げてから、福引器を作りました。振り替え出席のY3ちゃんも福引器を作りました。Mくんは自由工作で粘土作品をたくさん作りました。
 8日(金) 8日(金)
Mちゃん、Kくん、Tくん、Sちゃんは福引器から作りました。Mちゃんはデザインを工夫して、色を塗りました。Kくんは福引器の後、はんこも作りました。OKという英語です。上手に反転させてはさみでスポンジを切り、とてもきれいにスタンピングできました。Tくんは今日は集中力がありました。はさみで箱を切るのに苦心していましたが、一人で最後までしっかりと切りました。目打ちで穴をあけ、お箸で穴を広げるのは上手にできました。Sちゃんは絵具を早く乾かすのにドライヤーを使いました。ビニールテープをうまく巻いていました。Eちゃんは、はんこから作りました。好きな絵を描いて、スポンジを切りました。絵具をつけてスタンピングしました。そこから発展させようと思ったのですが、福引器を作りたいと希望しました。時間が少なかったので、色は塗らずに、本体のみを作りました。
 9日(土) 9日(土)
Dくんは福引器を作りました。キラキラテープでデザインし、とても豪華になりました。Hちゃんは福引器をおみくじに見たてて、どんぐりにも工夫をしていました。Tくんも福引器を作りました。色にこだわり、ボンド絵具で本体をぬったので、乾かすのに時間がかかりましたが、丁寧にできました。Kちゃんもひとつ、ひとつの作業が丁寧です。時間をかけてじっくり作業をしていました。Aちゃんははんこを作りました。雪だるまをモチーフにしたのですが、白地に白い雪だるまでは見えないので、黒い紙に、はんこを押していきました。「なんだか寂しいから、お花を入れたい」というので、お花のモチーフも作りました。おとなしいですが、自分の作りたいイメージをしっかり持っていて、私にちゃんと伝えてくれるので、頼もしいと感じます。
 27日(水2,4) 27日(水2,4)
Rくん、Sちゃん、Y1ちゃん、Mちゃんは、はんこ作りをしました。Rくんはポケモンのモチーフを3種類作りました。はがきにはそれぞれ違う並べ方でデザインをしました。Sちゃんは門松をモチーフにしたいというので、一緒にデザインを考えました。最小のモチーフをつくり、組み合わせて、門松にしました。いのししもうまくできてお正月らしい雰囲気が出ました。Y1ちゃんはお花の形や、いのししの形を作りました。切込みが甘く形がはっきり出ないので、切り方を見てもらいました。気にいった形になったので、本番のはがきにデザインを工夫しながら押していきました。Mちゃんはテンプレートで、複雑な形でデザインをしましたが、スポンジをきる段階で、シンプルな形に変更しました。1まい、はがきをつくりました。Y1ちゃんとMちゃんは工作もしたかったらしく、はがき作りは気もそぞろで、時間があまりなったのですが、福引器作りに取り掛かりました。途中まで作ったので、続きは次回に持ち越します。Y2ちゃんは前回の続きで、冬の飾りを作りました。粘土でサンタさんを作り、リースには赤い毛糸でちょうちょうむすびをしました。後半ははんこ作りもしました。豚をモチーフにしてはがきを作りました。工作もやりたい!というのですが、もう終わりの時間だったので、次回みんなも続きをするので、そのときにすることにしました。Tくんは福引器を作りました。すこし遅れてきたのと、丁寧に、デザインをしていたので、途中で時間となってしまいました。続きは持ち越します。作りながら、みんなそれぞれ冬休みに遊びに行くところなど、お話ししてくれました。
12月のお楽しみ会は12月13日(水2,4)、20日(水1,3)、12月22日(金)、23日(土)、
プログラムは1、クリスマス工作2、ビンゴゲーム、3、ティータイム でした。
工作はスノードームでした。ペットボトルを使い穴のあいた、透明の塩ビ板で仕切りを作っています。上から発泡スチロール製の雪が降ってきます。コツはさかさまにしても、モチーフが落ちてこないようにしっかり接着することです。予想より、時間がかかりましたが、みんなそれぞれに、雪だるまやツリーなど、モチーフを工夫して、仕上がりました。お忙しい中たくさんの保護者も参加してくださいました。お手伝いもありがとうございました。
新春のお喜び申し上げます
2007年がスタートしました。昨年は「命」の大切さを改めて考えさせられる年でした。与えられた命を大切にして、誰もが生き生きと人間らしく生きていく力を育てるには、まず、自己肯定力が必要です。自分の存在を認められることで、他者にも目が向き、関わりをもつことが、生きていく力の源となります。つまり、「いま、自分はこう感じている」という表現ができると、それが他者とのコミュニケーションを図る道となってくれるのです。
現代は、テレビや、ビデオ、パソコンなどの視覚情報が多く、実際に体験したことはないのに、体験したかのように感じてしまうことが多くなっています。そこで、実際の生活を見つめ、そこから生まれる感覚を磨いていくことが必要となってくるわけです。子ども時代には、知識の量を増やしていくことより、自然や人間に触れ、物事を感じ取ることが大事です。イメージする力(想像力)は人間が人間らしく生きていくために欠かすことはできません。感覚や感情の働かない体験や経験は、イメージすることができません。実感するものがある体験や経験だけがありありと記憶をよみがえらせ、イメージ化することができるのです。
身体感覚、五感を磨き、育て、描くこと、作ることを通して、自分の思いを表現することに自信を持ってもらいたいと思います。テーマから生まれる、喜怒哀楽や葛藤、制作時に働く感覚や、感情を自分自身で意識して感じていくことが、感性を磨くことにつながります。表現というのは子ども自身の主体的な行為によるものです。表現しようとする子どもの意図や内容を聞き、共感しながら、語り合うことで、子ども自身が自分で、自分は何を、どう表現したいのか発見していくのです。そばにいる大人は、子ども自身がその発見をできるように働きかけなければなりません。こういうことを考えながら今年も、子どもたちの豊かな感性を伸ばし、想像力の翼を広げられるよう、お手伝いをしたいと思っています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 2007年1月 日俣雅美
|
|
| [ こども図画工作教室 ] |
 |
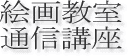
■会費制の通信講座です。 |
< デッサン・油絵・水彩画 >
全国どこからでも参加できます。
[ Click
] |
|
|